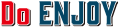| 観光案内 |
城めぐり
高松城 (史跡高松城跡 玉藻公園) |
高松城は日本三大水城のひとつ。北と東が瀬戸内海に面し、西南に標高200mもの石清尾山が要害となり、南は讃岐平野に開けるという、典型的な「後ろ堅固」の水城です。
現在も一部が残っている内堀や、外堀に海水を引き込み城の周りに幅の広い堀が三重に巡らされるという、海上に浮かんで建つような美しく堅固な城でした。遺構として残る月見櫓、続櫓、水手御門、渡櫓、艮櫓(うしとらやぐら)などが重要文化財に指定され、城内は史跡高松城(玉藻公園)として良好な保存状態を保っています。現在は見ることのできない天守も復元へ向けての取り組みが活発に行なわれているのです。
現在も一部が残っている内堀や、外堀に海水を引き込み城の周りに幅の広い堀が三重に巡らされるという、海上に浮かんで建つような美しく堅固な城でした。遺構として残る月見櫓、続櫓、水手御門、渡櫓、艮櫓(うしとらやぐら)などが重要文化財に指定され、城内は史跡高松城(玉藻公園)として良好な保存状態を保っています。現在は見ることのできない天守も復元へ向けての取り組みが活発に行なわれているのです。
〒760-0030
香川県高松市玉藻町2-1
香川県高松市玉藻町2-1

周辺の店舗・施設
|
食事
|
麺処 綿谷 高松店
香川県高松市南新町8-11
|
屋嶋城跡 |
屋嶋城は「やしまじょう」ではなく、正しくは「やしまのき」と呼び、築かれたのは667年(天智6年)と伝わっています。唐と新羅の連合軍に攻め滅ぼされた百済を助けるために日本が出兵した白村江の戦いで、日本軍は大敗して敗走しました。その後、唐や新羅の侵攻に備えるため対馬から九州、瀬戸内海沿岸を経て大和に至るまでの地域にいくつかの朝鮮式山城を築いた内のひとつが屋嶋城です。
遺構が少なく、その実体はよく分からなかったのですが、1998年(平成10年)に屋島の南麓山上部で石積みが発見されたのをきっかけに発掘調査が始まりました。その後、城門遺構なども発見され、全体像が分かるように。調査結果に基づいて城門遺構整備事業が行なわれ、2016年(平成28年)から一般公開されています。
遺構が少なく、その実体はよく分からなかったのですが、1998年(平成10年)に屋島の南麓山上部で石積みが発見されたのをきっかけに発掘調査が始まりました。その後、城門遺構なども発見され、全体像が分かるように。調査結果に基づいて城門遺構整備事業が行なわれ、2016年(平成28年)から一般公開されています。
〒761-0111
香川県高松市屋島東町屋島山上
香川県高松市屋島東町屋島山上

丸亀城 |
丸亀城は1597年(慶長2年)に生駒親正(いこまちかまさ)と生駒一正(いこまかずまさ)が築いたのが始まりとされ、当初この城は「亀山城」と呼ばれていました。
丸亀城は織田信長の居城である安土城や、豊臣秀吉が築いた大阪城の構造を参考にして造られているのが特徴です。天守がある城郭だけでなく城下町や武家屋敷を整備し、これらを囲む土塁を造って守りを固めました。
その後、丸亀城は本格的な近世城郭に改築され、現在は日本一高い石垣の城として知られており、現存天守12城のひとつとなっています。また、国指定史跡、国指定重要文化財、県指定有形文化財にもなっているのです。
丸亀城は織田信長の居城である安土城や、豊臣秀吉が築いた大阪城の構造を参考にして造られているのが特徴です。天守がある城郭だけでなく城下町や武家屋敷を整備し、これらを囲む土塁を造って守りを固めました。
その後、丸亀城は本格的な近世城郭に改築され、現在は日本一高い石垣の城として知られており、現存天守12城のひとつとなっています。また、国指定史跡、国指定重要文化財、県指定有形文化財にもなっているのです。
〒763-0025
香川県丸亀市一番丁
香川県丸亀市一番丁

周辺の店舗・施設
|
食事
|
麺処 綿谷 丸亀店
香川県丸亀市北平山町2-6-18
|